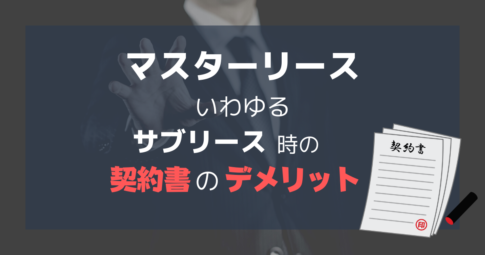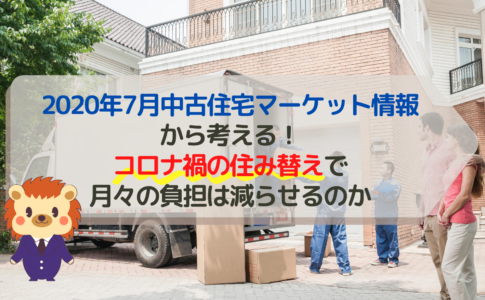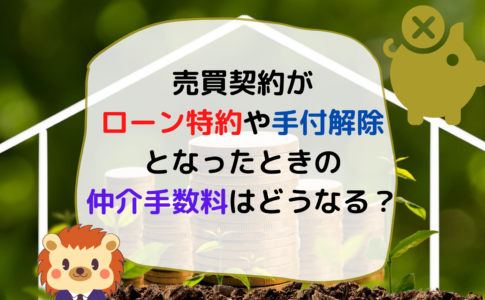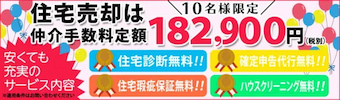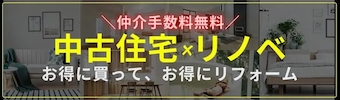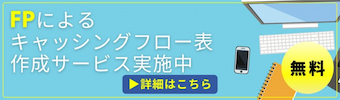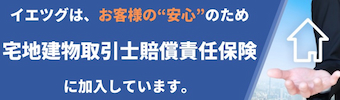不動産契約をする前に行われる重要事項説明。この重要事項説明がIT化し、テレビやパソコンを通じて行われることが可能になります。デジタル化が進む現代社会において、これからの不動産契約はどのように変化していくのでしょうか?
そこで本記事では、IT重説に関する以下の疑問にお答えしていきます。
- だれがどうやってIT重説を行うの?
- どんな社会実験が行われているの?
- 売買契約でIT重説はどのように役立つ?
実は現在IT重説が本格運用されているのは、不動産の賃貸契約のみ。売買に関しては、2019年10月から運用実験が開始されます。
今回は、全国59の実験事業者の内の1社である弊社イエツグが、わかりやすくIT重説を解説いたします。不動産業界の流れをチェックしておきたい方や、遠方の物件購入などを検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
YouTubeアプリやブラウザ版YouTubeでの視聴はこちら

不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士
目次
不動産売買におけるIT重説とは?

IT重説は、IT(インターネット通信)と重説(重要事項説明)を掛け合わせたものです。
これまで重要事項説明は、店頭などで「説明する人(不動産業者)」と「説明を受ける人(売買する人」が対峙して行われてきましたが、IT重説では自宅にいながら重要事項説明を受けられることになります。
そもそも重要事項説明って?
重要事項説明と聞くと、多くのお客様が「難しい」「早く終わってほしい」という怪訝そうな顔をされます。
しかし、この重要事項説明は不動産契約において非常に重要なものであり、国土交通省で有資格者からの説明を義務付けられている大切なことです。
そもそも重要事項説明とは、
「こんな契約内容だとは聞いていない!」「知らないままで契約してしまった…」
このようなトラブルを未然に防ぐため、契約締結前に「権利に関すること」や「土地や建物の規制について」など、契約の概要についての説明を行うものなのです。
なんでIT重説がはじまったの?
重要事項説明のIT化を決めたのは、国土交通省です。国土交通省は、以下の目的のためにIT重説の運用を開始させました。
- 時間コストや費用コストを軽減させる
- 日程調整の幅を広げる
- 自宅などのリラックスできる環境での重説
- 本人が外出できない場合でも重説が可能にする
重要事項説の説明は、宅建士が事務所などで2時間前後の時間をかけて行うものです。
しかしITの導入により、お客様は「好きな場所で」「任意の時間に」重要事項の説明を受けることができるようになります。
意外とハードルが高いIT重説
一見画期的に思えるIT重説ですが、実は不動産会社にとってはハードルが高いもの。これまでの業務内容を大幅に変えてしまう可能性があり「便利そうだから明日からIT重説に変えますね」という訳にはいきません。
重要事項の説明は、宅建取引業法という不動産の法律に定められた業務のひとつです。
重要事項の説明は「宅地建物取引士という国家資格を有した者」が「宅建証を見せながら」「記名押印」を行うことが法律で義務化されています。
重要事項説明がIT化されても、この手順を省くことはできません。
このことから、IT重説化は以下の規則を守る必要があります。
- 図面や書類を理解できるように視聴環境を整えること
- 宅建士が重要事項説明を行える環境にあるか映像や音声を確認していること
- 宅建証を画面に映し出せていること
インターネット環境化であっても、これまで通り宅建士が宅建証を見せつつ、書面を確認してもらいながら重要事項説明を行うことが必要です。
また不鮮明な画像では、IT重説とは認められず、結局は対面式で行う必要がでてきます。
社会実験その1.賃貸取引におけるIT重説

まず国土交通省が行ったのは、賃貸借契約のIT化です。
2015年8月~2017年1月までの6ヵ月間「賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験」が行われました。まずは、売買ではなく取引額の小さい賃貸借契約のIT化からはじめた、というワケです。
結果から言うと、賃貸借契約のIT重説は成功し、実施件数25,607件のうちトラブル件数は0件となりました。これにより国土交通省は2017年10月1日より、賃貸契約のIT重説の本格運用を始めたのです。
IT重説に続いて書面もデジタル化へ
さらにIT化は重説だけには留まらず、重要事項説の説明書と契約書の電子交付(PDF化)に向けても動き出しました。この書面の電子交付については、2019年10月1日~12月31日まで社会実験が行われました。
デジタル書面の配布の流れは、以下の通りです。
- 不動産会社がパソコンでデジタル書面を作成
- ファイルを暗号化し契約者に送信
- 契約者が暗号化された書面を受領
- 電子証明書にチェックを入れる
書面がデジタル化されれば、認証はチェックボタンを押下するだけでよくなります。印鑑を押す必要はありませんが、別途書面が必要なときは押印が必要です。
社会実験その2.個人売買におけるIT重説

IT重説化の次のターゲットは、売買取引です。賃貸借契約のIT重説化が安全と判断されたため、国土交通省は売買のIT化に向けて動きだしました。
契約書の電子交付同様に、2019年10月より約1年間、個人を含む売買取引のIT重説化の社会実験が行われます。すでに2015年8月から法人売買取引の社会実験が行われていますが、IT重説が行われた件数はたったの3件であったため、法人契約のIT重説実験は引き続き行っています。
しかし、賃貸借契約のIT化が上手くいっても、売買契約ではより慎重にIT重説の運用をしていかなければなりません。なぜならば、賃貸と売買には大きな差があるからです。
売買取引のIT重説の注意点

賃貸取引と売買取引では、以下のような違いがあります。
- 賃貸借契約よりも売買契約時の重説の時間が長い
- 賃貸借契約よりも売買契約時の書面の枚数が多い
- 賃貸借契約よりも売買契約に関わる人数が多い
売買契約では、交付する図面や契約書の枚数が多く、また契約に関わる人も多いことから、必然的に重要事項説明の時間が長くなります。
一般的に賃貸借契約では重説の時間は30~60分ですが、売買契約の重説時間は60~180分ほど。約3時間、スマホやパソコンに向かって話を聞くことは、簡単なことではありません。
国土交通省では、この問題を解決すべく「必要に応じてIT重説の中止」する規約も追加しました。もし重説の途中で「気分が悪くなった」「都合が悪くなった」などの事情が起きた場合は、重要事項説明を中止して後日時間があるときに改めて行うことが可能です。
まとめ:アフターコロナにIT重説の普及が加速する可能性も!
社会実験が行われる不動産売買のIT重説。まだまだ課題点が残されているものの、スマホが普及している現代社会において、不動産業界のデジタル化は避けられないと感じています。
弊社イエツグでは不動産業界に新しい風を取り入れるべく、この度のIT重説の実験登録事業者となりました。これからの不動産業界を背負うために、画期的な取り組みにどんどんチャレンジしていきたいと考えています。
IT重説に興味のある方は、ぜひイエツグまでご相談ください。