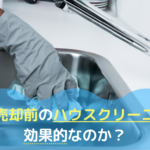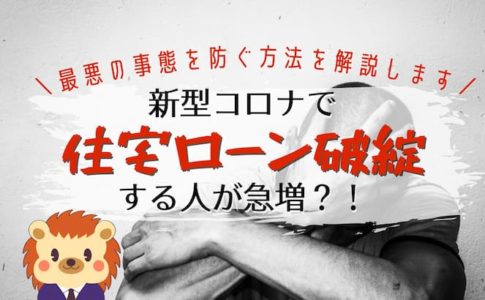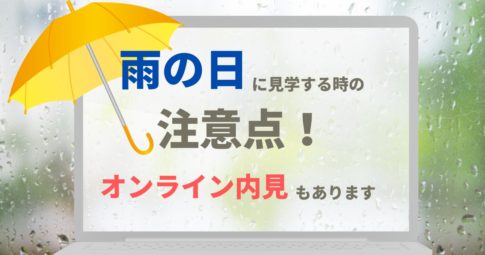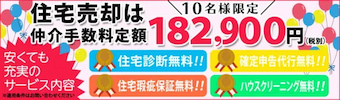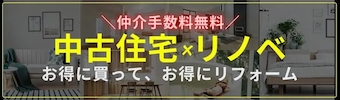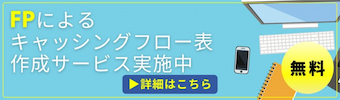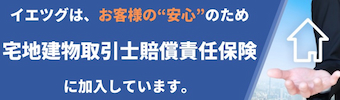2020年4月1日より、実に120年ぶりに民法が大幅改正されます。民法は不動産と切っても切り離せない法律ですので、この改正が不動産取引に与える影響は非常に大きいといえます。
とくにこれから不動産取引を考えている方が、今回の民法改正の中でとくに知っておくべきなのは、「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」に変わること。
なんだか両方とも難しい言葉ですが、簡単にいえば「契約不適合責任」となることで、 “不動産売買における売主の責任”が変わります。
とはいえ売主だけが関係あるものではなく、”買主が売主に対して請求できること”も変わるため、どちらの立場の方も必ず知っておくべきことなのです。
- 瑕疵担保責任ってなんだったの?
- 契約不適合責任になってなにが変わるの?
- 契約不適合責任になって注意すべきこと

不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士
目次
瑕疵担保責任ってどんな責任だったの?

改正民法前の「瑕疵(かし)担保責任」とは、“隠れた瑕疵”に対して売主が負う責任です。
そもそも「瑕疵(かし)」とは?
「瑕疵(かし)」は、日常的に使う言葉ではありませんが、不動産取引では多く使われます。
瑕疵とは、物件の不良箇所や欠陥をいいます。たとえば、雨漏りやシロアリ被害、土壌汚染などですね。
また物理的な瑕疵以外にも、心理的な瑕疵も様々考えられます。いわゆる事故物件やお隣がゴミ屋敷…のように、その物件には物理的な欠陥がないとしても、心理的に住むことが敬遠されかねない物件は、心理的瑕疵物件といわれます。
売主の責任対象は「隠れた瑕疵」
瑕疵担保責任は、物件の不良箇所や欠陥に対して売主が責任を負うものですが、対象は「隠れた瑕疵」に限られるという点がポイントです。
隠れた瑕疵とは、売買前のチェックで発見できなかったような瑕疵のこと。買主が容易に発見できる、壁の穴やフローリングの剥がれのようなものは隠れた瑕疵には該当しません。
物件引き渡し後に発覚した隠れた瑕疵について、発覚から1年間、買主は損害賠償請求ができます。ただし売主が不動産業者の場合、損害賠償請求ができる期間は、発覚から2年間です。
発覚した瑕疵が重大なものだとすれば、買主は契約解除の請求もできます。
「契約不適合責任」が不動産売買に与える影響は?

契約不適合責任の基本的な考え方
従来までの「瑕疵担保責任」は、売主に対し、「引き渡し後の隠れた瑕疵について責任を負いなさないよ」といったものでした。
しかし改正民法では、この「隠れた瑕疵」という文言が削除されます。
瑕疵担保責任に代わる契約不適合責任の考え方は、「契約の内容に適合したものを引き渡しなさいよ」というのが基本的な概念です。つまり、契約後の責任の対象としては「契約の内容に不適合なもの」と解釈できます。
瑕疵担保責任については、発覚した瑕疵が“隠れていたかどうか”がしばしば問題になっていました。
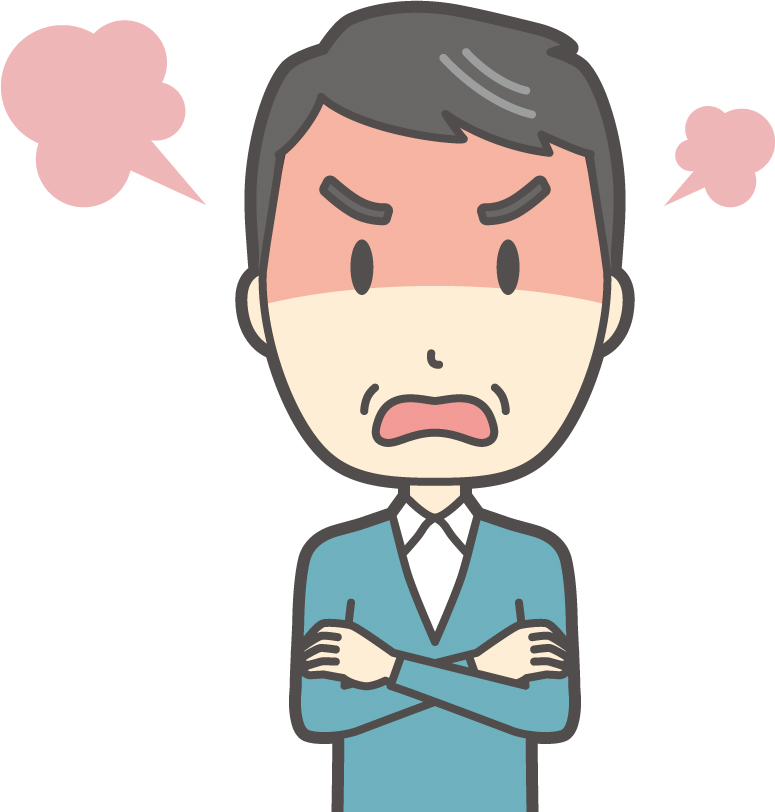
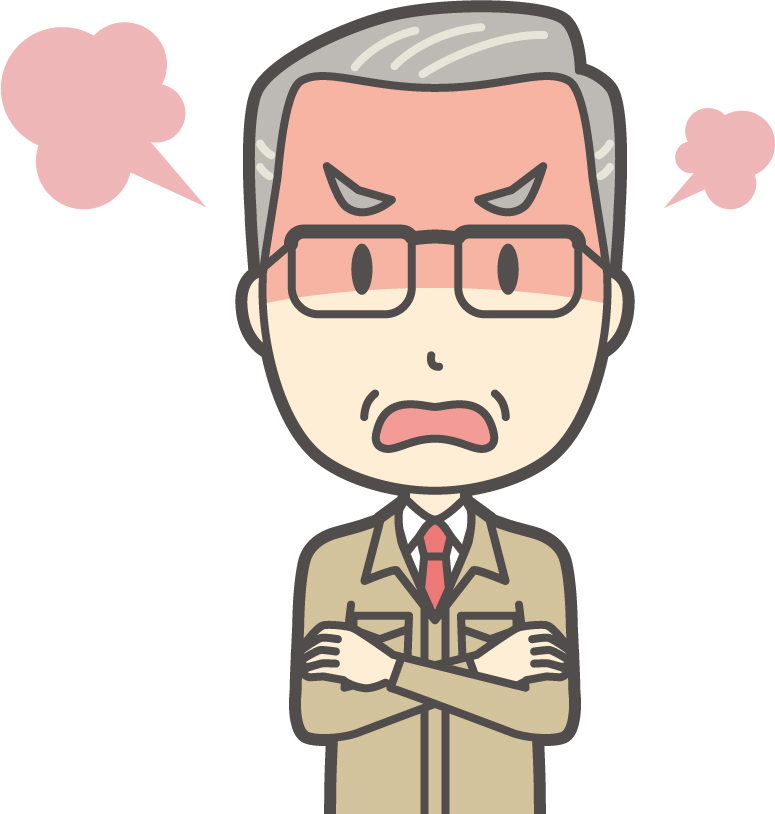
このような感じで、訴訟に発展するようなこともあったのです。
売主の責任の対象が「契約の内容に不適合なもの」となることで、売主や買主が「知っていた」「知らなかった」のではなく、契約書の内容が客観的に、明確に判断されることになります。
つまり、契約不適合責任が施行となってからは、従来以上に契約書や重要事項説明書、物件状況報告書の内容が重視されるようになるということです。
買主の請求権が増える
瑕疵担保責任では、隠れた瑕疵が発覚すれば、売主に損害賠償もしくは契約解除の請求ができました。それが契約不適合責任となることで、「追完請求」と「代金減額請求」ができるようになります。
それぞれの請求権については、次項から詳しく解説します。
契約不適合責任における5つの買主の請求権

1.追完請求(改正民法562条)
引き渡された物件が、契約に適合していなかった場合、買主は売主に対して履行の追完を請求できます。具体的には、「修繕」や「代替物との交換」によって、契約に適合させるよう請求ができます。
追完請求は、売主の責任履行のための買主による主となる請求権です。以下、解説する権利は、追完請求が履行されなかったときに取る対応策のような権利となります。
2.代金減額請求(改正民法563条)
追完請求が履行されなかった場合、買主は売主に対し、物件価格の代金の減額を請求できます。
追完請求はしたけれど、「どうやっても修繕ができない」「売主が修繕に向けて動いてくれない」といったときに認められるのが代金減額請求なので、まずは追完請求が先です。
減額されるのは、「その不適合の程度に応じた代金」と、改正民法で規定されています。
3.催告解除(改正民法541条)
追完請求したにも関わらず、売主の履行がない場合には、催告解除も可能です。
ただし、民法改正では、「社会通念に照らして軽微」な不履行については解除ができないとしています。
4.無催告解除(改正民法542条)
契約内容と重大な不適合があった場合には、買主は無催告にて契約の解除ができます。
重大な不適合とは、以下の3つと規定されています。
- 債務の全部の履行が不能であるとき
- 売主が履行を拒絶する意思を明確に示したとき
- 一部が不履行の場合、または一部の履行を売主が拒絶した場合に、残存する部分のみで契約の目的を達することができないとき
5.損害賠償請求(改正民法415条)
契約不適合責任では、瑕疵担保責任と同様に買主は売主に対して損害賠償請求ができます。
ただし、損害賠償請求ができるのは、売主に帰責事由があるときのみです。つまり、契約内容と不適合があっても、売主の過失によらないものであるのなら、損害賠償請求はできないとうことになります。
契約不適合責任は「任意規定」である点に注意!

契約不適合責任は、瑕疵担保責任と同様に「任意規定」です。
任意規定とは、当事者が決めていない場合に備えた標準的な備えであり、当事者同士が合意すれば別の定めが許容されます。
従来までも、売買契約書の特約欄に「売主の瑕疵担保責任も免責とする」「売主による瑕疵担保責任が生じる期間は2ヶ月とする」といった記載がされる取引がありました。契約不適合責任になっても、この点は変わりません。
売主も買主も、「契約不適合責任が~」という話なると(なんだか難しそうな話…不動産会社さんに任せちゃおう)などと思いがちになるでしょう。
しかし、責任の範囲や期間によっては、自身が不利な立場になる可能性が十分にあります。そのため必ず、わらかなければ担当者に質問し、少しでも自分が不利にならない売買契約を結ばなければなりません。
まとめ:瑕疵担保責任から「契約不適合責任」になることで、契約内容を確認する重要性が増す
瑕疵担保責任から契約不適合責任になることて、売主の責任対象は「隠れた瑕疵」から「契約に適合していないもの」にかわります。
そして買主の請求権としては、まずは「追完請求」。続いて「減額」や「解除」などの請求権が与えられます。
従来までは「隠れた瑕疵が発覚したので損害賠償を請求します」とやや曖昧な請求だったものが、「この点が契約と適合していないので、適合するように修繕等してください」となることで、対象と請求が明確になるという点が一番変わるところでしょう。
ただし契約不適合責任もまた、瑕疵担保責任と同様に特約事項の記載によって免責や一部免責とすることができます。民法改正後も、特約欄を含めて売買契約書の隅々まで目を通すことは怠らないことが大切です。
もちろん弊社イエツグでは、お客様に不利にならないご契約をしていただけるよう、サポートさせていただきます。