自宅などの不動産を購入する際には、多額の資金が動きます。
この多額の資金を調達する際には、夫婦で貯金を出し合ったり、夫名義で住宅ローンを組んだり、それでも不足するような場合は両親からの援助を受けるケースが大半でしょう。
このように複数人で不動産を購入した場合は、「この不動産を誰がどれくらいの割合で保有しているのか」を税制上、定めなくてはなりません。
これが「持分」です。
この記事では、不動産の「持分」について解説し、持分割合の決め方について説明していきます。しっかりと理解していただくことで、無駄な税金を払わずに済むようになります。
これから不動産を購入する方、取得する方が記事を読み終えたときには、自身で不動産の持分割合を決めることができるよう丁寧に解説していきます。
目次
そもそも不動産の持分ってなに?
持分割合とは
不動産を複数人で共有した際、共有者それぞれの所有割合のことを持分割合といいます。
この持分割合は、自由に決めても問題ありません。
不動産を購入した場合、不動産のお引渡し(ご決済)日に司法書士によって不動産の登記がなされます。
登記簿謄本と呼ばれる書類にあなたが決めた持分割合を記載し、司法書士は不動産の所有権移転登記をする必要があります。
そのため、ご決済日に
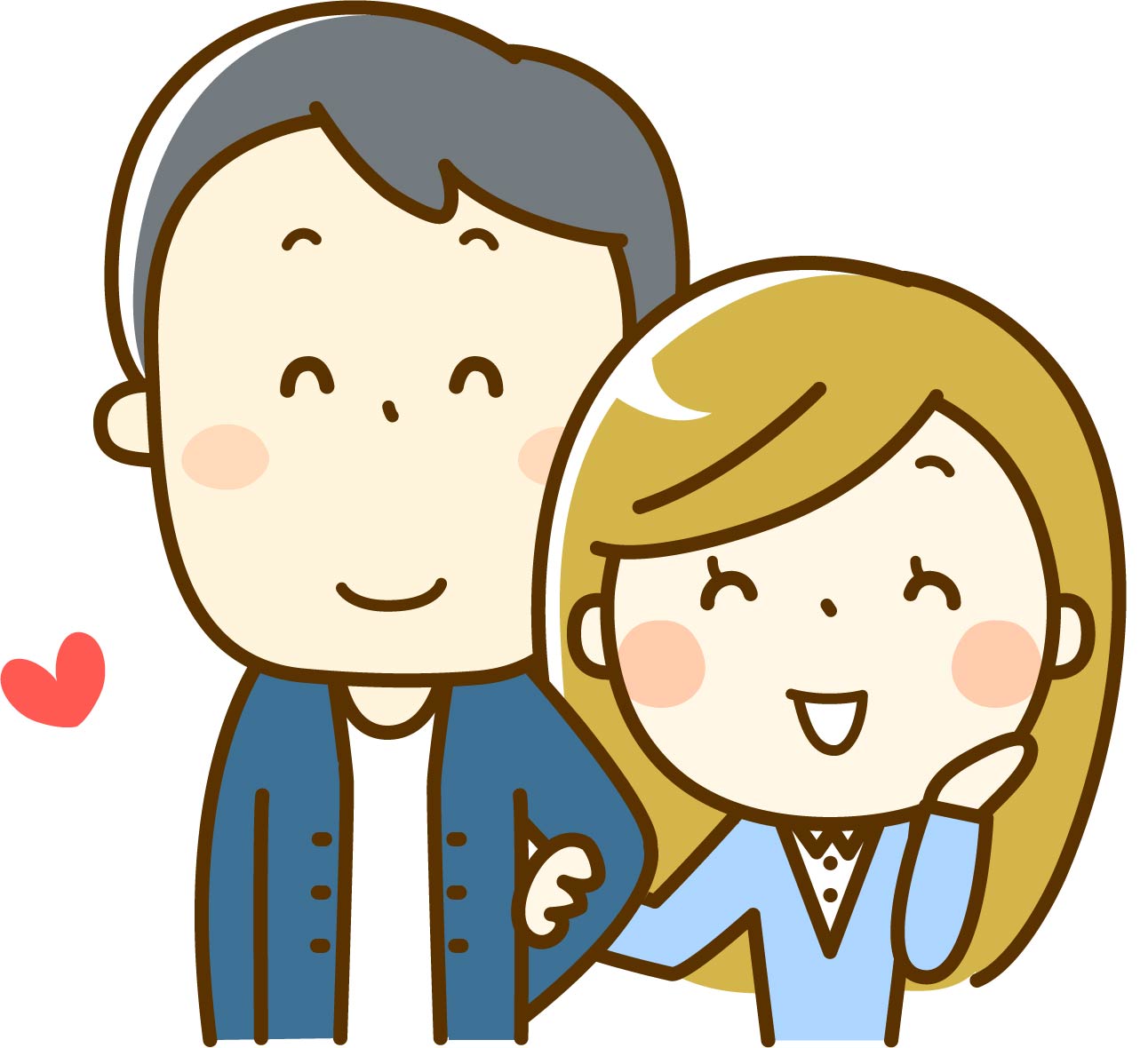
私たちは夫婦だから、持分割合は適当に半々で!
と簡単に決めてしまうことも可能です。
しかし、税法上のお話になると状況は変わり、もしあなたが「余計な税金を払いたくない!」ということであれば、自由に適当に決めてしまうのはよろしくありません。
余計な税金を払わないためには、出資割合に応じて持分割合を決める必要があります。
例えば、
1,000万円の不動産について、妻が自分名義の貯金100万円を出したとしたら、持分割合は10%ということになり、ご主人が残り900万円を住宅ローンで借り入れた場合は持分割合90%になります。
どんな時に持分割合を決める必要があるのか
住宅を建てたら登記
住宅等を購入する場合は、不動産業者を介して購入するのが一般的です。
この時、
不動産業者からは

住宅の登記をするのに必要だから、持分割合を決めて下さい
と言われることでしょう。
持分割合は登記簿謄本への記載に必ず必要になるため、不動産購入の段階では算出しておく必要があります。
そもそも、
どうして住宅の登記をする段階で不動産の持分割合が必要なんでしょうか。
それは税金に密接に関係あるからです。

適当に夫婦で半分ずつの持分にしておこう!
などとすると税制の面で不利になる場合があるので、きちんと正しく計算しておくようにしましょう。
計算方法(持分割合の決め方)
一般的な計算方法
計算式は一般的には、
持分割合=(自己資金+住宅ローン)÷(物件価格+諸経費)
という計算式になります。
計算していく上で迷うのが自己資金、物件価格、諸経費ということになるでしょう。
一体どんなものが自己資金、物件価格、諸経費に該当するのか、次の項目で解説していきます。
不動産購入時の諸費用について詳しく知りたいという方は、下記記事を参考にしていただけますと幸いです。
自己資金や物件価格、諸経費について
自己資金に該当するもの
自己資金になるものには、
- 自分名義の貯金(自己の給料などを貯金したもの)
- 相続した財産
- 贈与税納入後の受け取り資金
- 住宅ローンによる借入金
- 自分の両親から借入金
などが該当します。
反対に以下のものは自己資金に該当しないので注意して下さい。
- 配偶者名義の貯金
※婚姻期間が20年以上の夫婦間では最高2,000万円まで配偶者控除を受けられる、おしどり贈与の特例があります。
詳しくはこちらでご確認ください。
- 親名義の貯金
- 義理の親からの贈与
物件価格に該当するもの
物件価格になるものには、
- 建物代金及び土地代金
- 解体費用
- 測量費用
- 建設費用
- リフォーム費用
- 建物に附設する設備品等の費用
などが該当します。
反対に以下のものは物件価格に該当しないので注意して下さい。
- 家具の購入費用
- 家電の購入費用
諸経費に該当するもの
諸経費になるものには、
- 不動産所得税等の各種税金
- 司法書士や弁護士等への報酬
- 仲介手数料
- 住宅ローンの各種事務手数料
- 固定資産税
- 都市計画税
などが該当します。
反対に以下のものは諸費用に該当しないので注意して下さい。
- 保険料(火災保険、地震保険等)
- 町内会費
- 引っ越し費用
実践!自分での持分割合の計算の仕方!

それぞれの代表的な3つのケースについて持分割合の計算方法について具体的に解説していきますので、参考にして下さい。
ケース1:夫のみがローン返済する場合
前提
- 物件価格及び諸経費の合計は5,000万円
- 妻は頭金200万円のみ負担、その他は夫が頭金300万円とローン負担4,500万円
計算結果(持分割合)
夫:(300万円+4,500万円)÷5,000万円=96%
妻:200万円÷5,000万円=4%
∴夫:妻=96/100:4/100
=48/50:2/50
(補足)
上記持分割合は約分して表記しましたが、
100分の〇〇として約分せずに不動産登記簿に記載することも可能です。
そのあたりはお好きな表記で問題ありません。
ケース2:親からの資金援助がある場合
前提
- 物件価格及び諸経費の合計は5,000万円
- 妻の父から1,000万円の資金援助受け
- 妻は頭金300万円のみ負担、その他は夫のローン負担3,700万円
計算結果(持分割合)
夫:3,700万円÷5,000万円=74%
妻:300万円÷5,000万円=6%
妻の父:1,000万円÷5,000万円=20%
∴夫:妻:妻の父=74/100:6/100:20/100
=37/50:3/50:10/50
ケース3:夫、妻、妻の父で均等保有する場合
前提
- 物件価格及び諸経費の合計は5,000万円
- 3人で均等保有したいと考えている。
計算結果(出資額)
3人が以下の金額を均等に出資:5,000万円/均等保有したいと考えている人数≒1,667万円
住宅を共有名義で購入するメリットやデメリット

持分割合について、誰かが100%にならない限り、その不動産は共有名義となります。
ここでは共有名義で住宅等を購入するメリット・デメリットについて解説していきます。
メリット
購入できる住宅が増える
夫婦が働いていれば、それぞれから資金を提供することができます。
また、
ペアローンや収入合算を利用する際、借り入れ金額を増やすことができます。
その結果、一人では手が届きにくかった不動産でも購入しやすくなり、購入できる不動産の選択肢が飛躍的に増えます。
住宅ローン控除を各共有者で利用できる
現行(令和4年1月時点)の住宅ローンの最大控除額は新築の場合一人年間35万円です。
5,000万円の不動産を夫の持分100%で購入した場合でも、住宅ローン控除は年間35万円までしか受けられません。
一方で、
夫婦が50%ずつの持分で購入し、住宅ローンも2,500万円ずつ負担した場合は、夫と妻の両方で最大25万円ずつ合わせて年間50万円分の住宅ローン控除を受けることができます。(年末時点のローン残高の0.7%控除されます。)
令和4年度の最新の住宅ローン控除について詳細は下記記事をご参照ください。
売却時の特別控除の金額が増える
将来的に住宅を手放して利益が生じた場合は、その利益に応じて所要の税金を納めなくてはなりません。
現在の法律では一定の条件を満たせば、一人当たり3,000万円までの売却益に税金が課せられない居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例という制度があります。
詳しくはこちらでご確認ください。
例えば、
売却して5,000万円の利益が発生したとして、夫の持分が100%であった場合は、3,000万円を超えた部分に税金が発生します。
もし、
夫婦が50%ずつの持分で購入した場合は、売却益は夫も妻も2,500万円分となるので、それぞれ3,000万円以下なので課税されないことになります。
デメリット
売却時に共有者全員の同意が必要となる
持分が99%であったとしても、残りの1%を保有している方の同意なしには売却できません。
つまり、
誰か1人でも売却に反対すれば自宅などを売却できないことになります。
また、
相続で共有者が増え、遠隔地の人などであればさらに交渉が難しくなり、売却手続きは難航することが予想されます。
購入時の諸費用が増える
複数人が住宅ローンを組む際によく利用されるペアローンの場合は、2本立ての様式となるために、事務手数料や登記免許税などの諸費用が余計に掛かります。
ペアローンについてはの下記の記事をご覧ください。
夫婦だと離婚時の対応が複雑になる

離婚後の不動産登記上の名義はどちらにするのか

住宅ローンの返済はどちらが行うのか

住宅に住み続けるのはどちらか
などといったことを決めなければなりません。
たとえこれらが決まったとしても、その後の手続きが複雑です。
離婚を前提に売却するとしても税制上のさまざまな手続き等が必要となってくるので、専門家等への相談が必要となってきます。
持分割合を決める時の注意点

割合に従って正しく登記
例えば、
5,000万円の住宅を購入した場合、実際には夫のみが5,000万円負担したにも関わらず、持分を夫婦で2,500万円ずつとした場合、夫から妻へ2,500万円の贈与があったとして計算されてしまいます。
この場合、
妻に贈与税が課される恐れがありますのでご注意ください。
住宅に持分がないと住宅ローン控除の対象外
住宅を妻名義、土地を夫名義にした持分とした場合、夫は住宅ローン控除の対象外となってしまいます。
なぜなら、
住宅ローン控除は居住する住宅に対する控除であるためです。
住宅ローン控除について詳しくは下記の記事で解説しております。
両親から贈与される資金は直系の子や孫が受領
夫が妻の両親から住宅購入費としてもらったお金で持分を計上した際、その金額は贈与とみなされて課税の対象となります。
一方で、
これが自分の両親からだった場合は、住宅取得等資金の贈与の特例で一定の条件を満たせば非課税になります。(令和4年1月時点)
| 住宅の種類 | 贈与税非課税限度額 |
| 耐震・省エネルギーまたはバリアフリー住宅 | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
詳細については、下記税制改正大綱PDFのp18以降をご参照ください。
税金については税理士や税務署へ必ず確認しましょう

持分割合によって税金が変わってくるというお話をしてきましたが、不動産屋はあくまで不動産のプロであって、税金のプロではありません。
また、
税法は時限立法といって多くは期限があり、特例なども非常に多く存在します。
不動産を購入する際に本やネットで税金に関する費用についてリサーチされるかと思います。
しかし、
最終確認として必ず税金については税理士や税務署へ相談をすることを強くオススメいたします。
まとめ
住宅等の不動産取得に当たっては、持分割合の決め方は非常に重要になってきます。
不動産業者から

夫婦半分ずつが妥当なのではないか
と言われても、ご自身で一度計算して算出するようにして下さい。
先ほど示したメリット・デメリット、そして税金等の面を考慮した上で、ご自身が最も利益が得られるように決めて欲しいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
この記事が契機となり、一人でも多くの方が幸せになることを心より祈念して執筆を終わらせていただきます。
ちなみに弊社にてご紹介できる物件であった場合、諸費用として不動産購入時にかかる仲介手数料は無料+売主報酬55%プレゼント(キャッシュバック)もしくは仲介手数料定額18万2,900円(税抜)にてお手伝いしております。
さらに、
不動産売却においても、通常の不動産会社に依頼する場合は成約価格の3%+6万円の仲介手数料が掛かりますが、イエツグでは売却に係る仲介手数料も定額18万2,900円(税抜)で可能です。
また、
本記事でお話しした通り税金についてのサポートも、弊社顧問税理士により無料でおこなうことも可能です。

仲介手数料はできるだけ安くしたい、でもサポートは手厚く!
そんな欲張りな貴方の為のサービスをご用意しておりますので、
不動産売買でお困りの方は是非弊社イエツグまでお問合せ下さい!




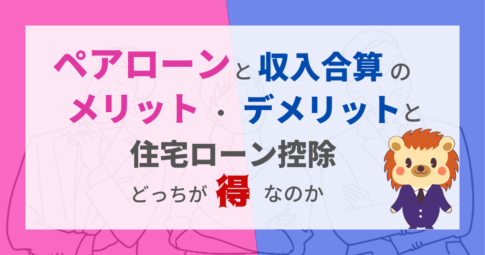


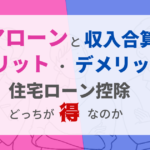
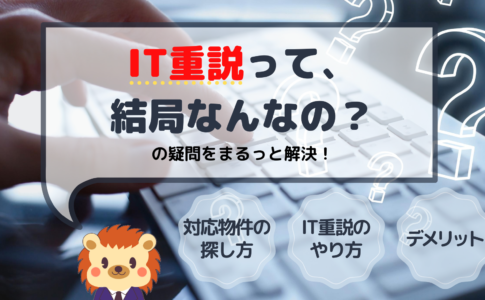
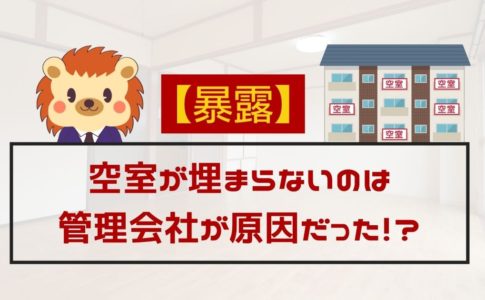
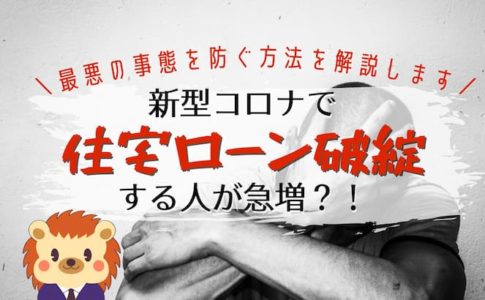
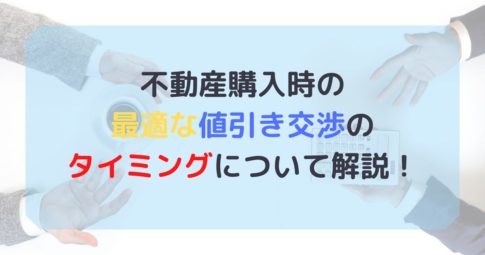

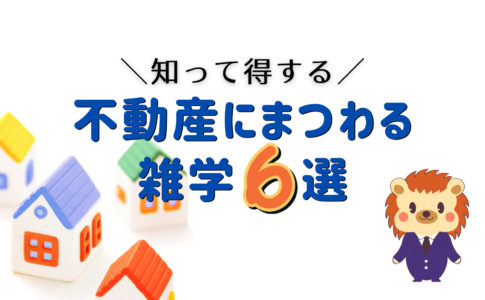

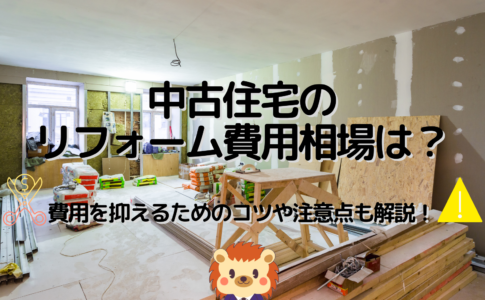






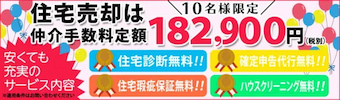


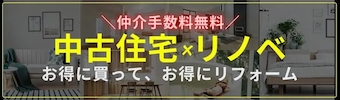
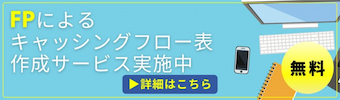
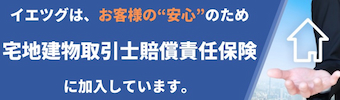
持分割合を決める必要があります。何対何にしますか?