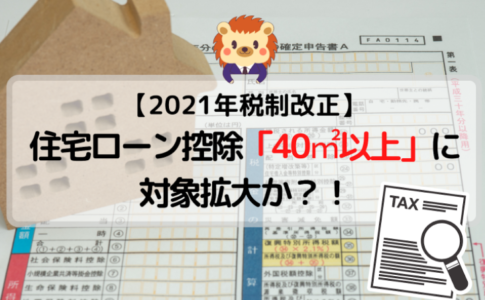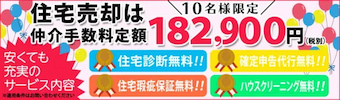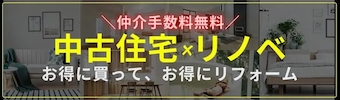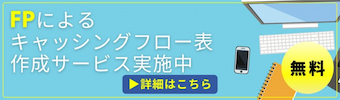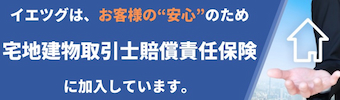不動産会社が不動産業(宅地建物取引業)を営むには、都道府県知事もしくは国土交通大臣からの免許が必要です。この免許発行にともない、不動産会社の業務は行政による規制の対象となっています。
しかし不動産会社はコンビニの数よりも多いといわれており、それだけ違反行為の数も膨大。行政がすべての違反を把握するのは困難です。そのため消費者に不利な違法行為の被害をうけないよう、消費者側の自衛が重要とされています。
今回は不動産会社が起こしやすい違法行為をケース別に解説。トラブルに巻き込まれないよう、怪しいポイントを学びましょう。
- 仲介会社による違反行為
- 売主業者による違反行為
- 違反にならない不動産会社の行為
- 違反行為の発覚経路

不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士
意外とズルいことをしている会社もあるから注意!
目次
不動産会社の違反1. 仲介会社の違反行為

1. 取引態様の虚偽
大手ポータルサイトに掲載される物件広告に、必ず記載される項目が「取引態様」です。取引態様は物件と掲載者の関係を示すものであり、誰がその物件を売りに出しているかによって、以下のように表記されます。
- 売主 = 売主本人
- 代理 = 売主から契約する権限を与えられた代理人
- 仲介、媒介 = 売主と媒介契約を結んだ不動産会社
- 一般 = 一般媒介契約を結んだ会社。同一物件を複数の会社で扱う際に使用される
- 専属専任、専任 = 専属専任、専任媒介契約を結んだ会社。原則として1社のみが扱う
これらは消費者をだます虚偽の表示のため、行政による監督処分の対象です。
2. 専属専任・専任媒介契約の不履行
売主が不動産を売却する際、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。
その中でも1社とのみ専属的な契約を結ぶ「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は、不動産物件データベース「レインズ」への登録や、売主への定期的な営業活動報告などの義務が課せられます。
これらの義務を1つでも遵守しなかった場合、不動産会社は監督処分の対象とされます。しかし悪質な不動産会社は自社に有利な状況作りを優先。レインズへの登録を行わない、営業活動報告をしないなど、専属専任または専任媒介契約の義務を果たさないケースがあります。
さらには3ヶ月の媒介契約期間終了後、勝手に自動更新される場合もあります。自動更新の条項は原則として何日前までといった期限が設けられていますので、売主はしっかりと契約書の内容を確認しておきましょう。
3. 事前説明や根拠がない実費請求
仲介手数料は売買が成立を前提とする成功報酬です。そのため、売主がなんらかの理由で売却を止めてしまうと、不動産会社は一切報酬を受け取れません。
しかし売主が契約途中で売却を止めた場合には、不動産会社はそれまでにかかった経費を売主へ実費で請求できます。その際には事前の媒介業務に関わる費用見積もりの提示や、使った経費の領収書をまとめた資料などが必要です。
悪質な不動産会社はこれらの取り決めを無視し、実費以上の費用や成立しなかった取引に対する仲介手数料を求めてきます。あくまで認められているのは経費の実費分だけです。明確な根拠がない費用請求は監督処分の対象ですので、払う必要はありません。
だまされないように契約書はしっかり確認しよう!
不動産会社の違反2. 売主業者の違反行為

そのため不動産会社が売主となり、不動産会社ではない買主に物件を売買する際には、個人間の売買よりも厳しい監視の目が向けられます。
ただ中には、不動産の専門性を活かし、買主に不利なような契約を交わす売主業者も存在しています。
1. 民法より不利な契約不適合責任
購入した不動産が契約内容と一致しない場合、売主は「契約不適合責任」に基づき、補修や代替物提供の義務を負います。
従来では、売主が負う責任は「瑕疵担保責任」として、事前に検知していなかった不具合に対してのみ責任を問われていました。これが2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」に変更。より広い範囲の問題に責任を負うように改正されています。
悪質な不動産会社はこの契約不適合責任から逃れようと、契約書に契約不適合責任を無効とする特約をひそませます。買主にとって非常に不利な条件となりますので、特約内容は十分に注意して確認しましょう。
2. 限度額を超えた手付金の受領
不動産購入の契約時に買主が支払う手付金は、物件価格の20%が上限です。手付金の支払いには買主の解約権を担保する目的があり、買主は手付金を放棄することで、売買契約の解除が認めらます。
悪質な不動産会社は解約をさせないように、物件価格の20%に留まらない手付金を要求する場合があります。もし買主が不動産会社の請求通りの手付金を支払ったなら、受け取った不動産会社側が監督処分の対象となるでしょう。
全部が全部違法行為とも限らないんだ。
不動産会社との「契約前」は違反にはならない

しかし当然ながら、トラブルのすべてが違法行為とは限りません。そのため監督処分や指導の対象とならず、解決に時間と手間がかかるものもあります。
1. 契約前のトラブルは処分の対象外
ここまで紹介した違反行為の事例は、原則として契約後のトラブルが対象とされています。
民法や宅地建物取引業法は消費者保護を重視していますが、一方で契約を結ぶまでは消費者には当たらないため、トラブルになっても法律による保護は期待できません。
契約にはもちろん、「売買契約」のみならず、仲介を依頼する「媒介契約」も含まれます。
ただ仮に媒介契約も結んでいない状況でトラブルが発生したとしても、不動産会社を罰する法律はほとんどないのが現状です。
2. トラブルに見舞われたら不動産会社を乗り換え
契約前のトラブルが罰則の対象にならなくても、客として不動産会社を信頼できなくなってしまうことでしょう。
もし不動産会社の対応に満足ができず、それでも違反行為に該当しないような場合には、不動産会社の乗り換えも検討しましょう。
不動産会社の対応は仲介手数料の有無によっても、品質が大きく左右されます。安い仲介手数料ばかりに注目するのではなく、信頼できるパートナーになれるか、真摯に対応してくれるかといった点を重視しましょう。
どうやって違反行為って見つけられるんだろう?
不動産会社の違反行為はどうやって発覚する?

その中で違反行為が発覚するには、2つの大きな理由があります。
1.行政による立入検査
行政による不動産会社への立入検査は、不正発覚の大きな理由のひとつです。
立入検査では主に次のようなポイントを調査します。
- 専任宅建士の在籍確認
- 従業者証明書の携帯
- 業者票、報酬額票の掲示
- 帳簿や従業者名簿の備え付け
これらの検査により、対象の不動産会社が営業に必要な法令を遵守しているかを確認しています。
ただしあくまで営業のための法令確認が中心であるため、現場の状況は検知できません。そのため個々の顧客とのトラブルを浮き彫りにするのは難しいでしょう。
2.消費者からの通報・相談
顧客とのトラブル検知に有効なのが、消費者からの通報・相談です。
悪質な不動産会社は法令違反を犯すだけでなく、制度を悪用した手口も使ってきます。これらの問題は行政による調査では表面化しにくいため、知識を持った消費者からの通報が非常に有効です。
まとめ:不動産会社の違反には冷静に対処しよう
不動産会社は、不動産売買を成功に導くパートナーとなる存在ですが、残念ながらすべての不動産会社が誠実とは限りません。不用意な損害を受けないためにも、消費者側も知識を身につけ、冷静に判断できるようにしましょう。
弊社イエツグは、不動産売買の仲介を専門とする渋谷の不動産会社です。綿密なコスト管理により、売買成立時の仲介手数料を一律182,900円(税抜)に設定。お客様の経済的なご負担を軽減した上でご満足いただけるよう、誠心誠意対応いたします。
不動産売買の成功には、何をおいてもお客様と不動産会社間の信頼関係が第一です。安心できる不動産売買のパートナーをお探しなら、ぜひ弊社イエツグまでお声がけください。