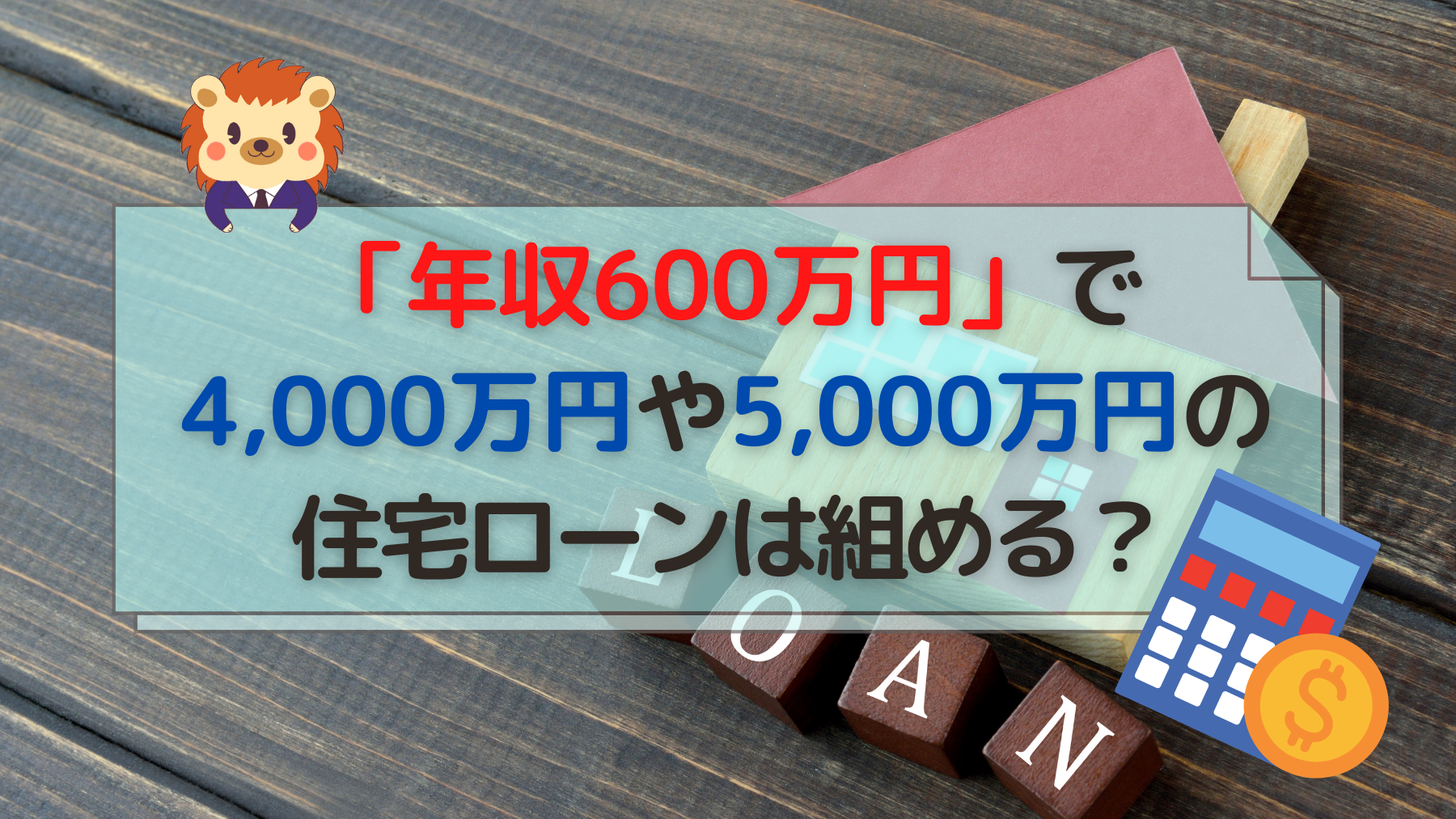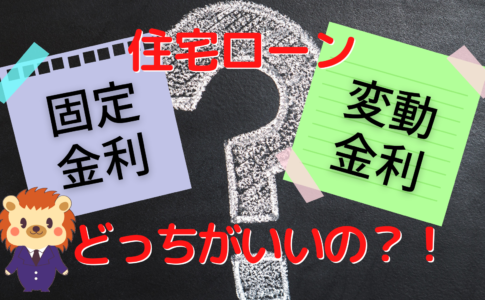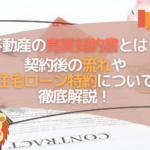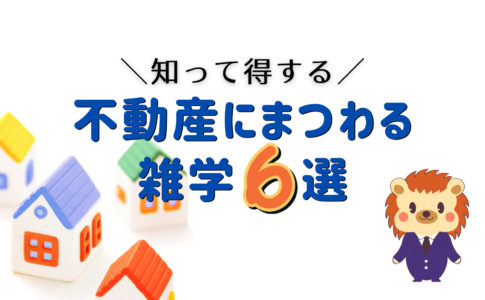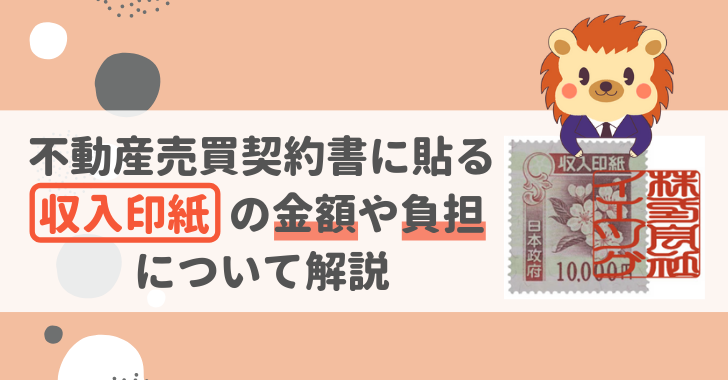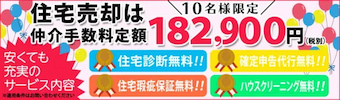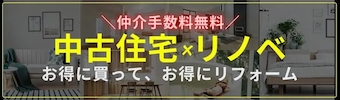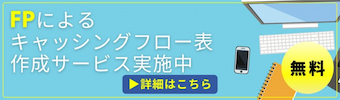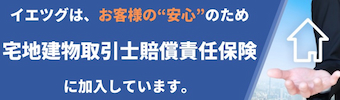金融機関は、年収600万円の方に対して4,000万円以上の住宅ローンを融資してくれる可能性があります。しかし、年収600万円あれば、誰でも4,000万円以上の住宅を購入できるわけではありません。
額面の年収が同じでも、手取り収入は個人によって違います。また、手取り収入が同じでも、その他の借入があれば限度額は下がります。いずれにしても住宅ローンの借入額は、毎月返済していける金額をもとに慎重に決めることが大切です。
この記事では、年収600万円の方が金融機関から借り入れできる住宅ローンの額や、現実的な借入額の決め方、資金計画の立て方などを幅広く解説します。
- 年収600万円の住宅ローン借入限度額
- 年収600万円の方の現実的な借入額
- 住宅購入時に準備すべき自己資金の決め方
【動画目次】
00:00 はじめに
01:15 1.年収600万円の人の住宅ローン借入限度額をシミュレーション
02:48 2.年収600万円の人の「現実的な」借入額
04:47 3.年収600万円で還付される住宅ローン控除額とシミュレーション
09:45 まとめ

不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士
目次
年収600万円の住宅ローン借入限度額を計算してみよう

まず金融機関が、年収600万円の方に対していくらまでの住宅ローンを融資してくれるのか計算してみましょう。
金融機関は、住宅ローンの借入限度額を以下の計算式を用いて算出しています。
借入限度額=(年収×返済比率÷12−他の借入返済額)÷「審査金利◯%で100万円を◯年借りた場合の毎月の返済額」×100万円
※「審査金利◯%で100万円を◯年借りた場合の毎月の返済額」はこちらの表で確認できます
「返済比率」「審査金利」の定義と目安は、それぞれ以下の通りです。
| 内容 | 目安 | |
| 返済比率 | 年収のうち住宅ローンの返済に充ててもよい割合 | ・年収400万円未満:30% ・年収400万円以上:35% ※フラット35の場合 |
| 審査金利 | 金融機関が住宅ローンの審査をする際に用いる金利 | ・変動金利:3.1〜4.0% ・固定金利:借入金利と同じ |
変動金利は、返済途中の金利が状況に応じて上下する金利タイプ
固定金利は、返済途中の金利が変わらない金利タイプ
上記の計算式にある「他のローンの返済額」とは、マイカーローンや教育ローンなどで毎月返済している金額です。他のローンを返済していると、住宅ローンの借入限度額は少なくなります。
ここで、以下の条件で住宅ローンの借入限度額を計算してみましょう。
- 年収:600万円
- 返済比率:35%
- 返済期間:35年
- 審査金利:3.5%
- 審査金利3.5%で100万円を35年借りた場合の毎月の返済額:4,133円
- 他の借り入れ返済額:なし
・借入限度額=(年収×返済比率÷12−他の借入返済額)÷「審査金利で100万円を○年借りた場合の毎月の返済額」×100万円
=175,000円÷4,133円×1,000,000円
≠4,230万円
年収600万円で4,000万円の住宅は買える?現実的な住宅ローン借入額の決め方

住宅ローンの借入額は、金融機関が貸してくれる額ではなく、ご自身が返していける額をもとに決めることが大切です。
年収600万円の場合、額面収入から税金や社会保険料を差し引いた手取り年収は、約460〜480万円。よって毎月の手取り収入は、ボーナスも考慮すると30〜32万円となります。
手取り収入32万円のうち、 返済比率を35%に設定し毎月17.5万円の住宅ローンの返済に当ててしまうと、残りの14.5万円で生活をしていかなければなりません。
さらにマンションを購入した場合は、管理費や修繕積立金、駐車場代の支払いが必要です。戸建て住宅を購入した場合は、将来の修繕や増改築に備えて積み立てが必要でしょう。
以上の点から、現実的な返済比率は25%以下といわれています。以下は、2020年10月現在の金利水準をもとに、返済比率15〜25%の住宅ローン借入額を逆算した結果です。
| 返済 比率 |
返済可能額 | 住宅ローンの借入額の目安(返済期間35年、元利均等方式) | |
| 変動金利(0.475%) | 固定金利(1.3%) | ||
| 15% | 毎月75,000円(年間90万円) | 2,900万円 | 2,550万円 |
| 20% | 毎月100,000円(年間120万円) | 3,900万円 | 3,400万円 |
| 25% | 毎月125,000円(年間150万円) | 4,850万円 | 4,200万円 |
例えば、毎月10万円を返済に充てられる場合、変動金利型の住宅ローンを3,900万円借り入れられるため、自己資金を100万円用意すれば4,000万円の物件を購入できます。
しかし変動金利は、将来的に金利が変動して毎月の返済負担が上昇するリスクがあることを、忘れないでください。たとえ4,000万円の物件が買えるとしても、返済負担が増えたときに滞納する恐れがあるのなら、借入額を少なくする必要があります。
手取り収入のうちいくらを返済に回せるのかは、家族の人数や年齢、住む場所によって、大きく異なります。住宅ローンを借り入れたあとに生活が苦しくならないよう、現実的な借入額を設定しましょう。
年収600万円の人は住宅ローン控除を活用すべし

住宅ローン控除とは、年末時点における借入残高の1%に相当する金額を所得税や住民税から控除してくれる制度です。たとえば年末時点の借入残高が3,000万円の場合、所得税と住民税の負担を最大で30万円軽減できます。
控除期間は最大で10年ですが、所定の条件を満たすと、控除期間が13年に延長される特例措置が実施されています。特例措置が適用された場合の、返済11〜13年目の住宅ローン控除額は、以下のうち少ない金額です。
- 住宅ローンの借入残高の1%
- 建物取得価格の2%÷3
ただし住民税から控除できるのは、所得税の課税所得金額の7%(上限13万6,500円)が上限です。また年収が同じ600万円であっても、家族構成や生命保険の加入状況などによって、節税効果が異なる点に注意しましょう。
住宅は「頭金」がなくても購入できるが「手付金」と「諸費用」の支払いは必要

ひと昔前は、住宅を購入する際に物件価格の2割の頭金が必要でしたが、2020年10月現在は頭金がなくても住宅を購入できます。
たしかに頭金を準備できていると、住宅ローンの借入額が減って毎月の返済負担や利息額を減らせます。しかし頭金の準備に時間がかかると、住宅ローンの借り入れが遅れて、完済予定が75歳や80歳などの高齢になり、返済負担が老後の生活を圧迫するかもしれません。
よって物件の購入資金を、生活に支障が出ない範囲の借り入れと、自己資金で賄えるのであれば、物件価格の2割の頭金がなくても購入できます。
ただし住宅の購入時には、諸費用の支払いが必要です。諸費用は、住宅ローンへの組み込みや諸費用ローンの借り入れで支払えますが、毎月の返済負担が増えるため、現金で支払うのが望ましいです。
また住宅の売買契約を結ぶときは、手付金の支払いが必要となるケースがほとんど。住宅を購入するときは、諸費用や手付金を支払えるだけの現金は準備しましょう。
手付金を支払う意味と相場
手付金とは、不動産の売買契約時に、買主が売主に対して支払う金銭です。不動産の売買契約から引渡しまでに買主が契約を破棄した場合、手付金は売主に没収されます。物件の引き渡しが完了すると、手付金は売買代金に充当される仕組みです。
手付金は、売買代金の5~10%程度が相場。たとえば売買代金が3,000万円であった場合の手付金は、150万~300万円となります。
諸費用の相場
住宅の購入時に支払う諸費用の種類は、以下の通りです。
| 住宅購入に必要な諸費用 | 住宅ローンに必要な諸費用 | その他の諸費用 |
| ・仲介手数料 ・手付金 ・印紙税 ・登記費用 ・保険料(火災保険 地震保険) |
・保証料 ・事務手数料 ・団体信用生命保険料 |
・引っ越し費用 ・新調する家具家電の購入費用 |
諸費用は、物件価格の6〜9%ほどかかるのが一般的です。例えば、3,500万円の住宅を購入する場合、諸費用の目安は210万〜315万円。中でも仲介手数料は、法律で定められた上限額である「物件価格×3%+6万円」に設定している不動産会社が多いため、高額になりやすいものです。
そのため、自己資金が不足して諸費用の支払いが困難な場合は、仲介手数料が安い不動産会社に仲介を依頼するのも一つの方法です。
弊社イエツグの仲介手数料は、定額制の182,900円(税抜)ですので、購入時の諸費用負担を大きく抑えられます。また、今なら売主から仲介手数料をいただける物件は「仲介手数料+現金キャッシュバック」となるキャンペーンを実施しています。
イエツグにご相談いただくと、諦めていた夢のマイホームに手が届くかもしれません。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:年収600万円の方は慎重に資金計画を立てて住宅を購入する
年収が600万円ある方は、基本的にその他の借入がなければ4,000万円以上の住宅ローンを借り入れることも可能です。しかし実際の借入額は、手取り収入からいくらの住宅ローンを返していけるのかを考慮して決めるようにしましょう。
また住宅購入の際は、頭金が必須ではないものの、手付金と諸費用の支払いは必要です。住宅購入の資金計画を立てる際は、物件の価格や手付金、諸費用がそれぞれいくらで、購入費用を現実的な借り入れと自己資金で賄えるのかを考えましょう。
弊社イエツグには、FPや住宅ローンアドバイザーといった「資金計画」のプロが、あなたの住宅購入を精一杯サポートいたします。
仲介手数料も定額あるいは無料ですので、金銭的な負担を抑えつつ購入後も安心して暮らしていきたい方は、弊社までご連絡ください。

大手保険会社で培った知識と経験から、保険、不動産、税金、住宅ローンなど幅広いジャンルの記事を執筆・監修。